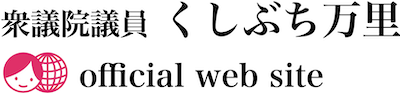【国会質問】FATF勧告とNPOの過度な規制?

内閣委員会で、11月11日(金)、「FATF勧告法案」について国会質疑に立ちました。
一般的には、とても分かりにくい法案なので、パネルを用意。
一言でいえば、金融面におけるテロ対策についてですが、
これは、「国際テロリスト財産凍結法」、「外為法」、「組織的犯罪処罰法」、
「麻薬特例法」、「テロ資金提供処罰法」そして「犯罪収益移転防止法」の、
6つの法律を改正するものです。
大量破壊兵器の拡散やテロ防止、マネーロンダリング対策などの必要性は、
もちろん、理解できるところです。
しかし、FATF勧告のNPO資金規制や報告書では
「NPOや市民社会セクターへの働きかけやガイダンスの強化が必要」と
されている点について、大きな懸念があります。
とくに、私自身、NGOで17年間、
人道支援や国際協力、環境保護などの分野で世界各地で活動してきた者として、
本日はそこに絞って、大臣に質問しました。
まず、「マネロン・テロ資金供与・拡大金融対策の推進に関する基本方針」に書かれた、
FATF勧告・項目8に関する「非営利団体の悪用防止」という項目について、
日本で、そうした事例があるかを大臣に尋ねました。
「一件もない」との答弁でしたが、では、なぜ過度に行う必要があるのでしょうか?
あくまでガイダンスであり、「制裁のようなものは考えていない」ことを引き出しました。

そもそも、国際社会から、2012年に採択された「FAFT勧告」では
項目8にテロ対策の文脈でNPOの資金規制が含まれていることに関して、
政府によるNPOなどへの国家監視が強められてきたことが問題視されています。
市民社会への弾圧に使われていることへの懸念の声は強いのです。
米国の団体「The Charity & Security Network」のレポートによれば、
各国政府が反政府活動の規制、市民社会への弾圧に
FATFが推奨する「金融規制」を活用している、
そのことを指摘する人権団体の声を紹介しています。

「調査結果が示すのは、FATF勧告・項目8が作り出した複雑なルールと規制によって、
NPOは国家による過剰な規制や監視にさらされる大きな危険性があり、
それが市民社会の組織にとっての運営上・政治活動上の可能性を制限してしまうことである。
指定されたテロリスト及びテロ組織のブラックリスト化等の
カウンターテロリズム措置に加えて、
勧告・項目8は、政府に市民活動の余地をさらに狭める手段を与え、
この場合、市民社会が発展し、紛争解決を行い、人権擁護活動をおこなうための
資金源にアクセスし、配分する自由を規制するのである」としています。
さらに、国連特別報告者からも、
このFATF勧告に対して、国際法違反につながる措置を正当化するとして、
厳しい批判がなされています。
それは、「FATFは国家により結社の自由を不当に規制されることから
市民社会部門を守るための特別な措置を提供できておらず、
国家による規制行為が、FATF勧告の項目8に沿ったものであるとお墨付きを与えている」
というものです。

実際に、NGOの友人にヒアリングしたところ、次のような事例が届きました。
◯ミャンマーがFATFの対象となったために、国内で民主派支援している人権団体がリストアップされ、資金調達が難しくなった。
◯ソマリアで支援をしている現地のパートナー団体へ送金する際に、FATFが影響して困難が生じ送金が滞った。
大臣の認識を問うたところ、「悪用防止に必要である」とする紋切り型の見解を
繰り返すにとどまりましたので、
法案にNPOを守るセーフガード条項を入れるよう強く提案しました。
最後に、財務省が自治体に対して、
「NPOをテロ組織」と関連づけるような通知を出していたことを問題視し、
その法的根拠を尋ねました。
財務省は、FATF勧告・項目8を法制化したものはないことを認め、
明確な根拠はなかったことが明らかになりました。
その後、反対討論を終えると、何人かの議員に声をかけられました。
自分自身のNGO/NPO経験からの視点と分かりやすい資料が評価されたのだと考えています。