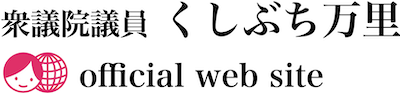COP24と地域社会

今日から、COP24がポーランドで始まっています。
それに先駆けて、先日開かれた IGES(地球環境戦略研究機関)のセミナーに参加しました。
なかでも、地域の再生エネルギーを軸にして脱炭素の町づくりに取り組んでいる事例は興味深いものでした。
具体的に、地元の自然資源を活用した自然エネルギーをつくり、それを地産地消して循環させることで、地域外に出ていくエネルギー費用の流出を減らし、その差益で生まれた財源で地域の課題解決に取り組まれています。
環境省の「地域経済循環分析」に照らすと、自分の町で、1年間にどれくらい域内の事業所が付加価値を稼いだか(生産)、どれだけ雇用所得になっているか(分配)、域内の所得がどれくらい消費と投資に回ったか(支出)、一方、外部からのエネルギー費で住民の所得がどれだけ流出しているのかがわかります。
皆さんの街はどうでしょうか。
www.env.go.jp/policy/circulation
登壇された小田原市(人口約20万人)の場合は、域内生産額が約6000億円強に対して、かつて約233億円のエネルギー費が域外へ流出。
下川町(人口約3000人)の場合は、
域内生産額215億円に対して約12億円。
それぞれ、地元の商工会議所やNPOと一緒に取り組み、独自に再生エネルギー条例や炭素会計をつくって、エネルギー自立をめざし、コスト削減分を子育て支援や社会保障、防災、公共交通やまちづくりに還元しています。
これから冬になりますが、健康の観点から、家の断熱や熱利用も重要。
年間ヒートショックで2万人も死亡する(ちなみに、交通事故死亡者の約4倍にもなります)のは確かに異常です。ドイツでは、断熱の概念は「人権」そのものだそうです。
環境にいいことは、地域にもとっていい。
人口減少社会でも安心して住める地域をつくる視点から、世界の気候変動の動きに注目したいと思います。